情報科学Tips
HALLO担当講師のブログです。情報科学に関するブログを月1回お届けしています。
記事一覧
| 2026年2月13日 |
|---|
| 2026年1月19日 |
|---|
| 2025年12月19日 |
|---|
| 2025年11月14日 |
|---|
| 2025年10月17日 |
|---|
| 2025年9月19日 |
|---|
| 2025年8月8日 |
|---|
| 2025年7月18日 |
|---|
| 2025年6月13日 |
|---|
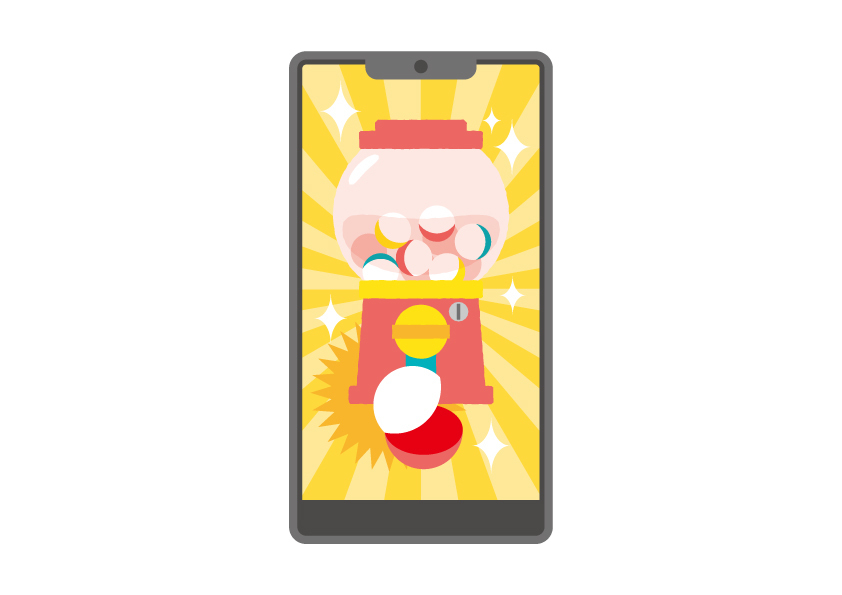
くじびきやおみくじ、ゲームの「ガチャ」、キャンペーンの抽選など、私たちの身の回りには「運で決まる」仕組みがたくさんあります。
しかし、インターネットやアプリの世界で行われているこれらの抽選は、実際にはランダムな数値(乱数)を使ったプログラムによってできています。
コンピューターが「1〜100の中からランダムに1つ選ぶ」といった計算を一瞬で行い、その結果に応じて当たりやはずれを決めています。
このときに重要なのが「条件分岐」です。
たとえば《1〜5なら大当たり、6〜30なら当たり、それ以外ははずれ》といったように、数値の範囲によって結果を分けて、当たる確率を設定します。「ガチャ」の排出率や、キャンペーンの当選確率は、こうした数値の区切り方でコントロールされています。
また、乱数は他にもあります。たとえば「7の倍数のときだけ特別な演出を出す」「下1桁が0ならボーナスを付ける」といった仕組みも、すべて数の特徴を条件として利用しています。
こうした工夫によって、見た目にはランダムでも、プログラムとしてはきちんとしたルールのもとで動く仕組みが作られています。
このように、乱数と条件分岐を組み合わせることで、抽選、ゲーム、キャンペーンの仕組みが成り立っています。
偶然に見える結果の裏側には、実はとても論理的で正確なプログラムの世界があり、それを理解することは、正しく使いこなす力につながっていくのです。
おうちで
チャレンジ!
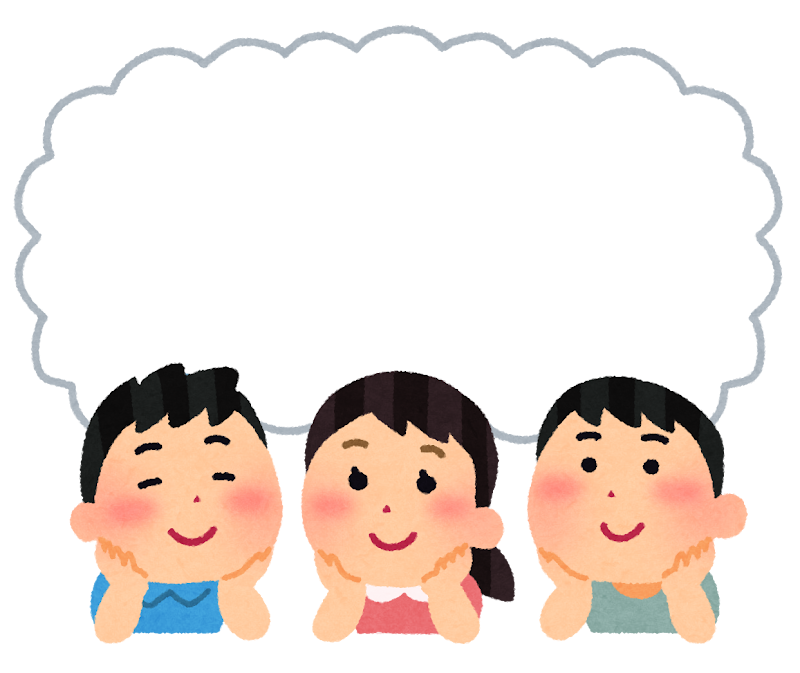
身の回りにある「運で決まる」ものは何があるかな?
探してみよう!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。

おうちで
チャレンジ!
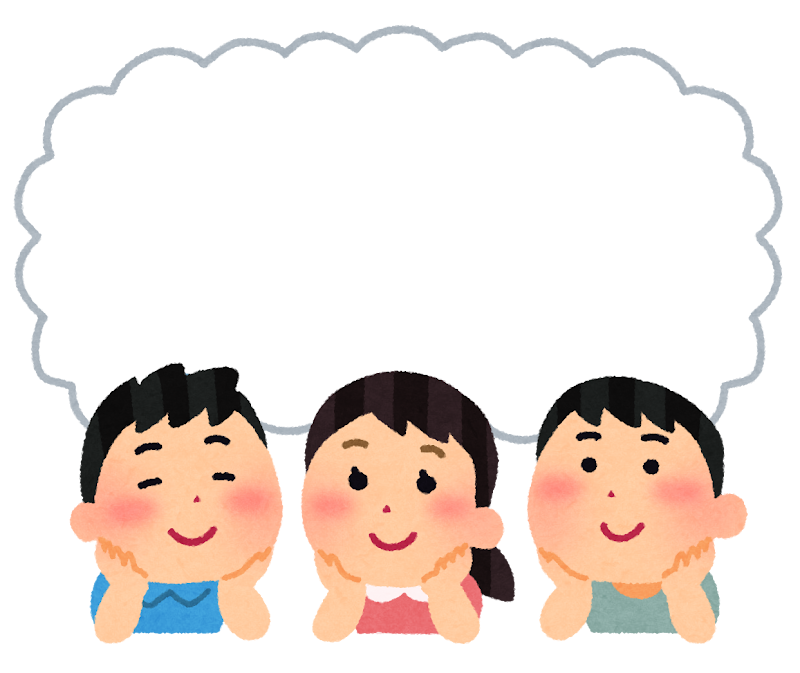
「o」「n」「e」を並び替えて作れるパスワードはいくつあるかな?
考えてみよう!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。
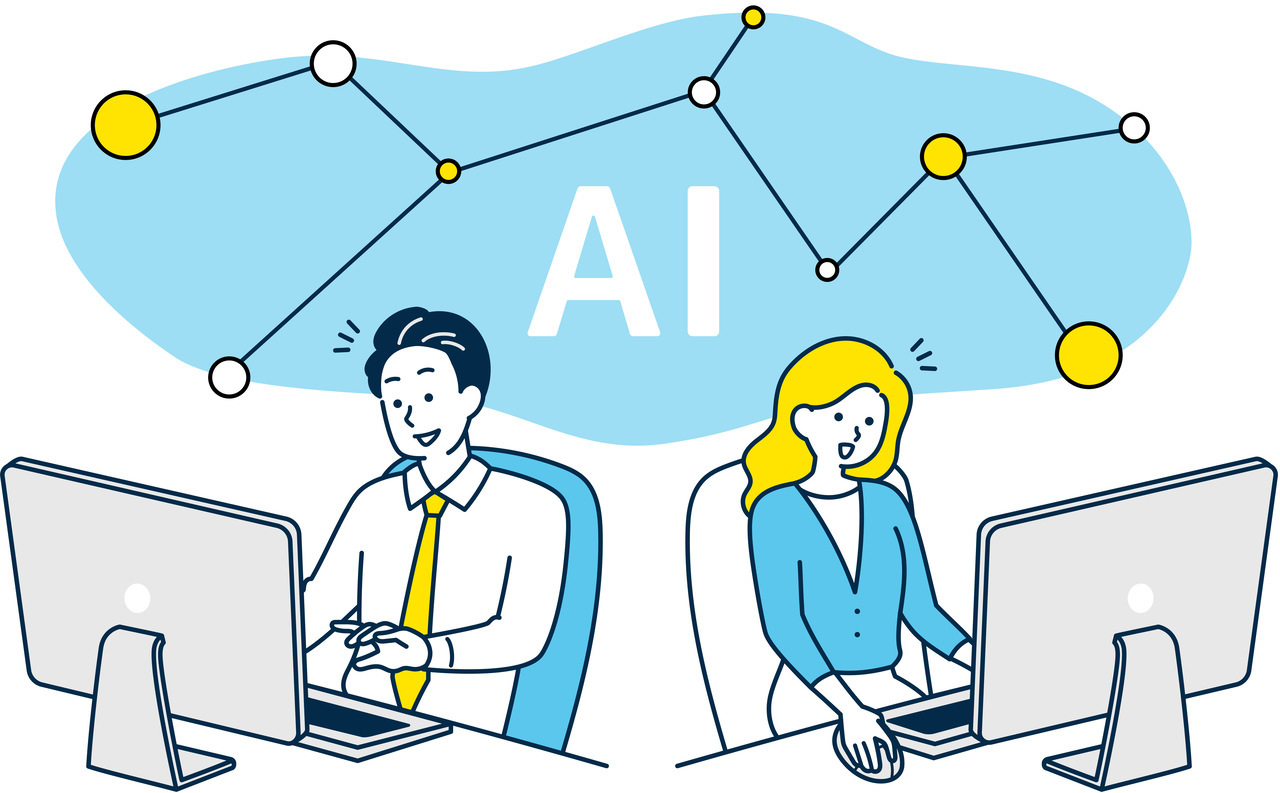
また、災害時には避難者名簿をAIが読み取ってデータ化し、支援の迅速化にも役立ちます。
ですが、私たちがAIに手書きの文字や数字を認識させてみると、うまくいかないこともあります。それは「AIが学習したデータ」と「現実の入力」に違いがあるためです。
AIは万能ではありません。
しかし、私たちがその特性を理解し、正しく使えば、社会をより正確で安全にする力となります。
おうちで
チャレンジ!
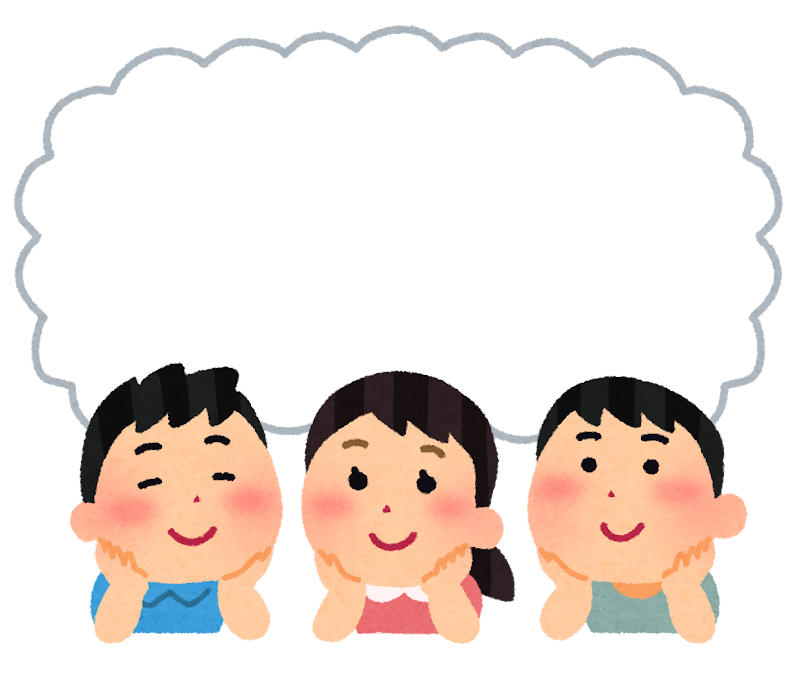
AIの時代。きみの字は読めるかな。
最近のテストは、コンピューター(AI)が字を読んで点数をつけることが増えてきています。
あなたの字は、AIが読みやすい字かな。
今日は家でノートに書いて、家の人に「読みやすい字かな?」と聞いてみよう。

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。
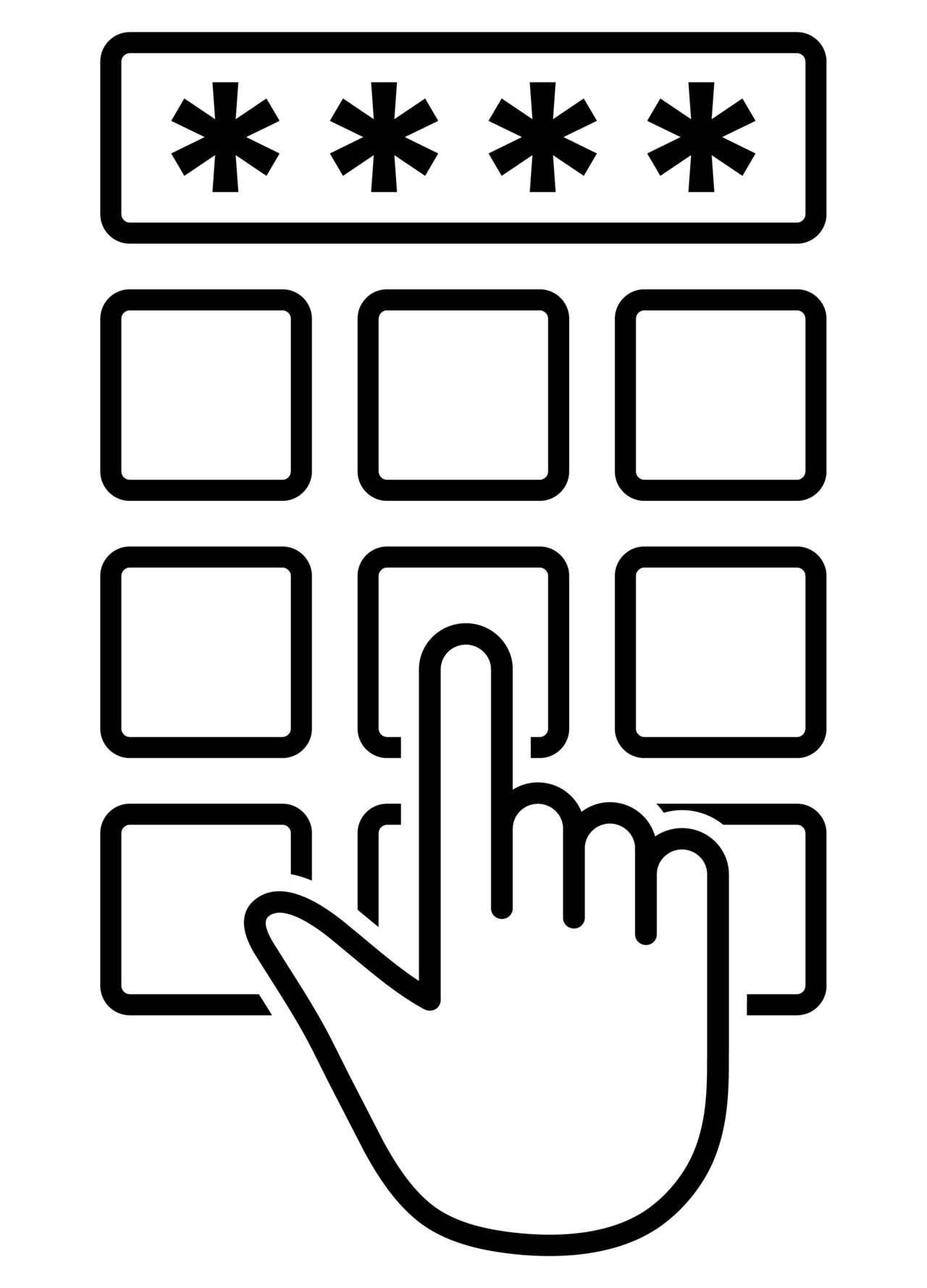
それは文脈によって大きな意味を持ち、社会のさまざまなサービスを動かす基盤となっています。
たとえば「123」という文字列を考えてみましょう。黒板に書かれていればただの数字ですが、銀行の口座番号ならお金のやりとりに使う大切な情報です。学校の講座番号なら科目を区別するための目印になりますし、オンラインショップでは商品番号として注文を処理するために使われるかもしれません。
つまり、同じ「123」でも、使われる場所によってまったく異なる意味を持つのです。
このような文字列は、コンピューターの内部では「0」と「1」の信号に変換されて扱われます。
たとえば、SNSで「ありがとう」と入力して送ると、それは「3042、12354、 …」といった文字コードの数字の列に変えられ、インターネットを通じてサーバーに送られます。
サーバーはその文字列を受け取り、「誰から」「誰へ」「いつ」といった宛先や送信元の情報と組み合わせて処理します。
そして結果を返すとき、受け取った側のスマホやパソコンはその数字の列をふたたび「ありがとう」という文字列に組み立て直し、画面に表示するのです。
このような文字列と、それを操作する方法(長さを調べる、比較する、置換する、大文字小文字を変える、数字やアルファベットだけを抜き出すなど)を理解することは、パスワードの生成や暗号化・復号化といった高度な仕組みにつながっていきます。
つまり、文字列を正しく理解することは、プログラミングやセキュリティの基礎であるだけでなく、現代社会で情報を安全にやり取りし、活用するための大切な第一歩なのです。
おうちで
チャレンジ!
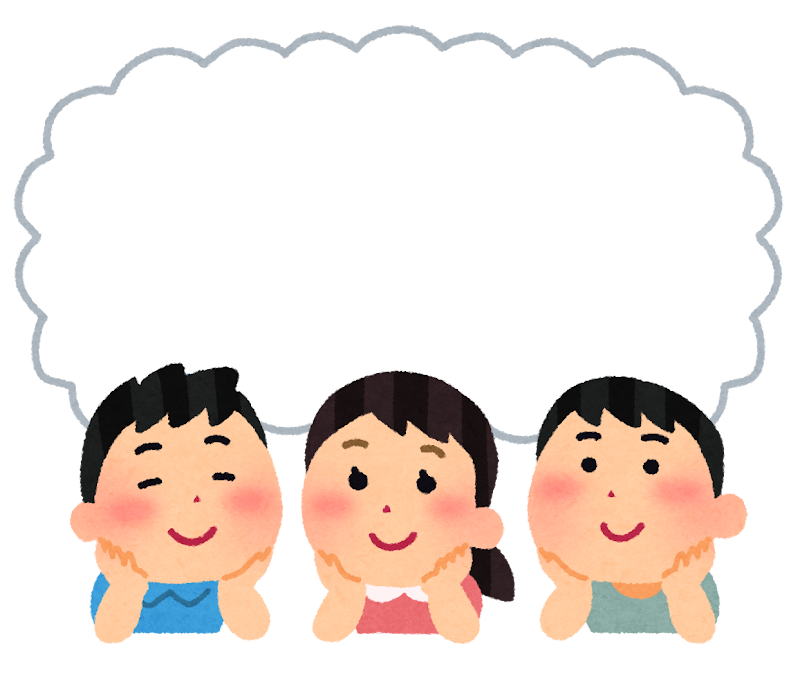
~前回からの続き~
前回の内容から、一部抜き出しました。
(全文が気になる人は、前回の記事を確認してください!)
――――――――――――――――――――――
(抜粋)今日は、風見町に引っ越してきてちょうど一週間。
明日は、町内の市に行ってみようかな。「風見マルシェ」っていうらしい。
――――――――――――――――――――――
質問「この内容を、ほんとうに知らない人まで見てもいいかな?」
①家族だけに見せたい ②友だちに見せたい ③だれでも見てもいい
【ヒント】この文には、「風見町」という町の名前や、「風見マルシェに行く」という行動の予定が書かれています。こうした情報があると、知らない人にも住んでいる場所や行動が分かってしまいます。そのため、安全のために「家族だけで見る」のがいちばん安心です。
→ 解答は「① 家族だけの方がいい」が良いのではないでしょうか。おうちのルールを考えてみてください!

おうちで
チャレンジ!
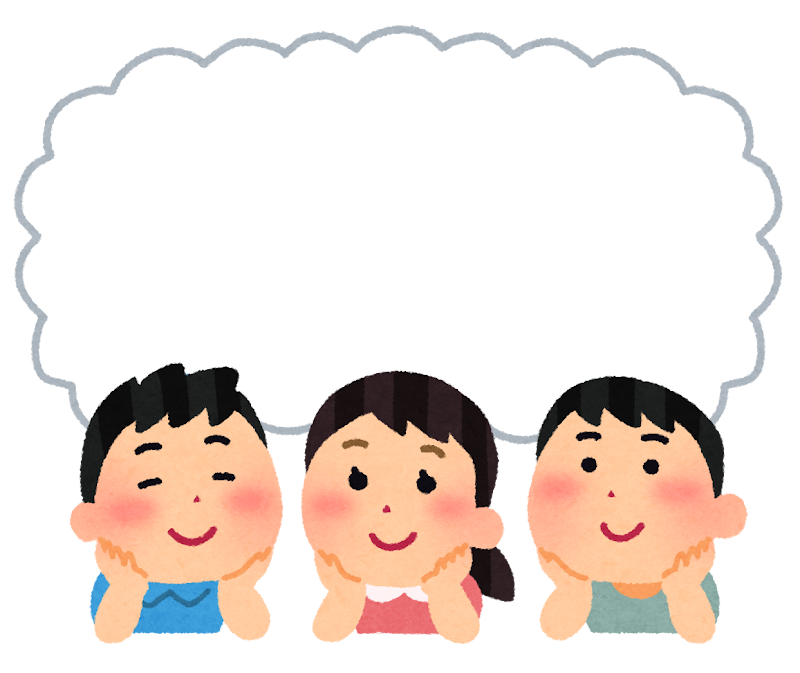
もしインターネット上に、あなたの日記や写真を「全世界に公開」すると、知らない人にも見られます。また、わるい人は限られた内容から、住所や通っている学校などの大切な個人の情報を特定してしまうことがあります。
次の文章はある女の子の日記です。下の質問について考えてみてください。
――――――――――――――――――――――
20××年〇月△日(□)
今日は、風見町に引っ越してきてちょうど一週間。
朝は、いつものように「風見坂」を登って、駅前の「風見珈琲店」へ。店主の三宅さんは無口だけど、豆の焙煎にはとことんこだわる職人肌の人。カウンターの端に座って、今日もカフェラテとシナモントーストを注文。
午後は、図書館で仕事。風見町立図書館はこぢんまりしているけれど、二階の閲覧室からは山並みがよく見える。
明日は、町内の市に行ってみようかな。「風見マルシェ」っていうらしい。手作りのジャムや陶器、古本なんかも出るらしい。
――――――――――――――――――――――
質問「この内容を、ほんとうに知らない人まで見てもいいかな?」
① 家族だけの方がいい
② 友だちまで見せてもいい
③ だれでも見てもいい
次回の更新で、解説します!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。

おうちで
チャレンジ!

考えてみよう!
――――――――――――――――――――――
もしAIが「宿題の答え」を全部教えてくれたら?
Q:それをそのまま写していい? それとも自分で考える時間も大切?
――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――
もしAIが「友だちの気持ち」を勝手に決めつけて答えたら?
Q:それを信じていい? 友だち本人に聞くほうがいい?
――――――――――――――――――――――

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。

おうちで
チャレンジ!
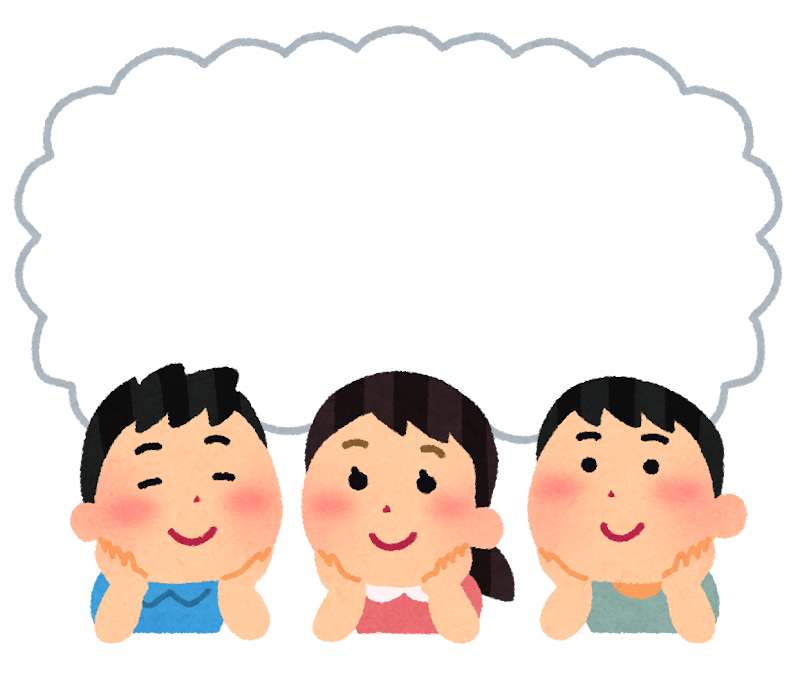
■例題(れいだい)
Q.「すいか」を一文字ずつ次の文字にすると?
ヒント:「す」の次は「せ」
こたえ:「せうき」
■問題(もんだい)
ちうぷあげつゅろあずきっぺ きうしうつょえ!
ぞふ しあきすとの!
※「っ」と「!」はそのままだよ!
※「ん」の次は「あ」だよ!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。

現代社会では、シンプルなルールとセンサー情報の活用により、さまざまな課題が解決されています。
例えば、核家族世帯の増加により家事の負担が問題視されていますが、遠隔操作ができるお掃除ロボットの普及により軽減されています。
この遠隔操作には、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)が活用されています。これは、インターネットを通じて家電を遠隔操作できる仕組みです。お掃除ロボットの他にも、スマートスピーカーや自動調理家電などがあります。
IoT家電の動作には、プログラミングの工夫が欠かせません。
例えばお掃除ロボットは、単にランダムに動くのではなく、センサーを活用して障害物や汚れの位置を検知し、最適なルートを選択します。その際に、変数や条件分岐を活用することで、状況に応じた柔軟な動作を可能にしています。例えば、「壁にぶつかったら90度回転する」「汚れを検知したらその場を重点的に掃除する」といったプログラムが組まれています。このように、シンプルなルールの組み合わせによって複雑な動作が実現されているのです。このようなプログラミングには、論理的思考力が求められます。掃除機が効率よく動くためには、どのようなルールを設定すればよいかを論理的に考え、無駄のないルートを導き出す必要があります。これは、まるでパズルのように試行錯誤を繰り返しながら最適な答えを見つける作業です。
このような思考力を育むことは、子どもたちの学習にも大きな意味を持ちます。問題解決力や創造力が養われ、将来のさまざまな分野で役立つ力となるのです。
おうちで
チャレンジ!
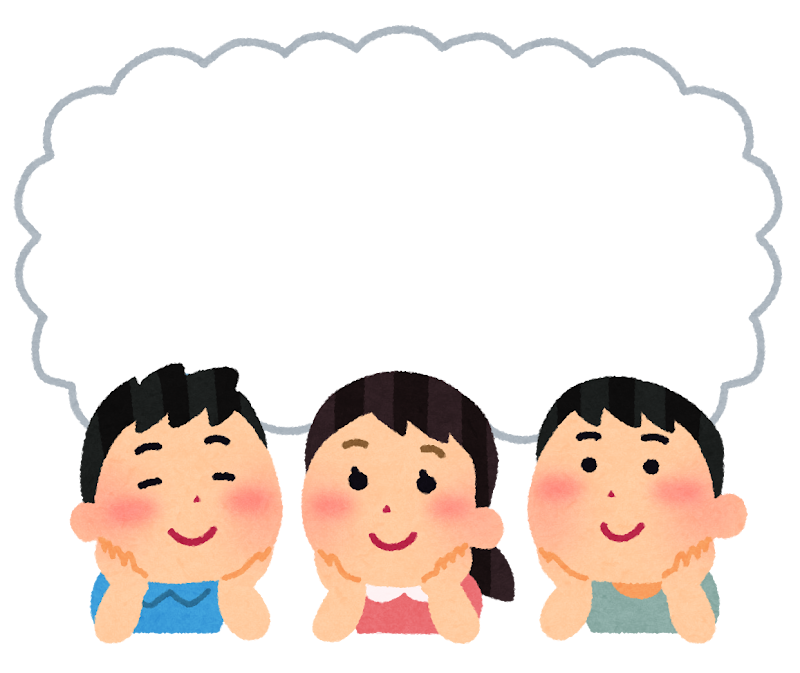
おうちにあるIoT家電は何かな?いくつあるかな?
探して数えてみよう!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。

コンピューターは、0と1の組み合わせで情報を処理しています。
この0と1の並びを「2進数」と呼びます。コンピューターが理解できる言葉です。
私たちが普段使う「10進数」とは異なり、2進数では0と1の2種類しか使いません。例えば、10進数の「3」は、2進数では「11」と表されます。こうした仕組みを理解することで、コンピューターの動作原理が分かるようになります。
プログラミングの世界では、「ビット演算」というものがあります。これは、0と1を使って計算を行う方法で、いくつかの種類があります。その演算を組み合わせることで、コンピューターは高速に計算を行っています。
ビット演算が利用されている技術の中に、ネットワークの分野で「IPアドレス」「サブネットマスク」という仕組みがあります。
IPアドレスは、インターネット上でコンピューターの住所のような役割を果たし、どの機器と通信するかを決めるために使われます。
一方、サブネットマスクは、IPアドレスの中で「ネットワークの部分」と「コンピューターの部分」を区別するための仕組みです。
ビット演算を学ぶことで、コンピューター全般の仕組みをより深く理解でき、プログラミングを社会に活かす方法を考える思考力を身につけることができます。
おうちで
チャレンジ!
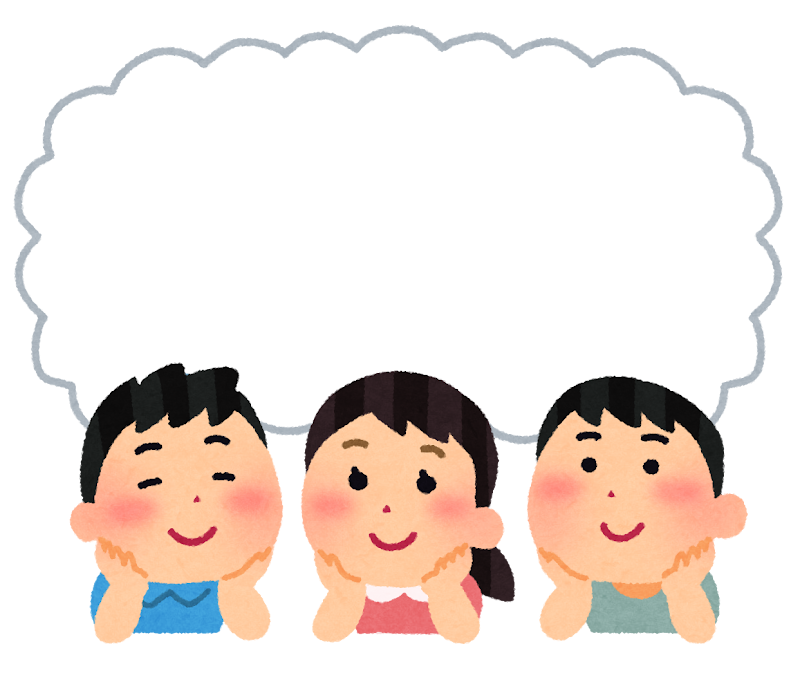
おうちのスマートフォン・パソコン・タブレット・ゲーム機のIPアドレスはいくつかな?
確認の仕方を調べてみよう!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。

日々の暮らしの中で、私たちは何気なくデジタル表示を目にしています。
時計の時刻表示、電卓の数字、家電の操作パネル――これらはすべて、必要な情報を瞬時に伝え、生活を便利にしてくれる存在です。
その根幹にあるのが、7セグメントLEDの仕組みです。7セグメントLEDとは、7つの小さなランプ(LED)を組み合わせて、数字や文字を表示する装置のことを言います。
この技術の核心にあるのは、1と0の組み合わせで成り立つ「ビット」の世界です。LEDの点灯・消灯を1と0で制御し、それを組み合わせることで、数字や文字を作り出しています。こうしたシンプルな論理の積み重ねが、複雑なデジタル表示を支えているのです。
わずか7つの光の組み合わせで多様な数字や記号を表現するこの技術は、デジタル表示の基礎となり、私たちの社会を豊かにしています。
デジタル表示に興味を持つことは、単なる知識の習得ではなく、電子工作や回路設計の理解へと発展し、未来の技術者や発明家の第一歩となります。
自分の手で動かしたLEDが、数字を形作る瞬間――その小さな成功体験が、次の挑戦へとつながっていきます。
そして、いつか子どもたちが生み出す技術が、誰かの役に立ち、社会をより良いものに変えていく日が来るかもしれません。
おうちで
チャレンジ!

「7セグメントLED」で数字を表示するとき、ランプはいくつついているかな?
0~9まで、考えてみよう!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。

インターネットが生活の一部となった現代では、ネットワークの仕組みやセキュリティを理解することが、単なる知識の習得ではなく、社会で必要なスキルの一つになっています。この学びは、プログラミングのスキルとも深く関係しています。
プログラミングを学ぶことで、コンピューターがどのように動くのかを理解し、情報を安全にやり取りする方法を考える力が養われます。
また、プログラミングを通じて「論理的に考える力」が身につくことも、セキュリティ対策に役立ちます。
不正アクセスを防ぐための仕組みを考えたり、情報が外部に漏れないようなプログラムを作ったりするには、問題を論理的に分析し、適切な対策を講じる力が必要です。
こうしたスキルは、プログラマーだけでなく、日常的にインターネットを利用するすべての人にとって重要なものです。
これからの時代を生きるうえで、プログラミングスキルとセキュリティ意識をともに高めていくことが大切です。
おうちで
チャレンジ!
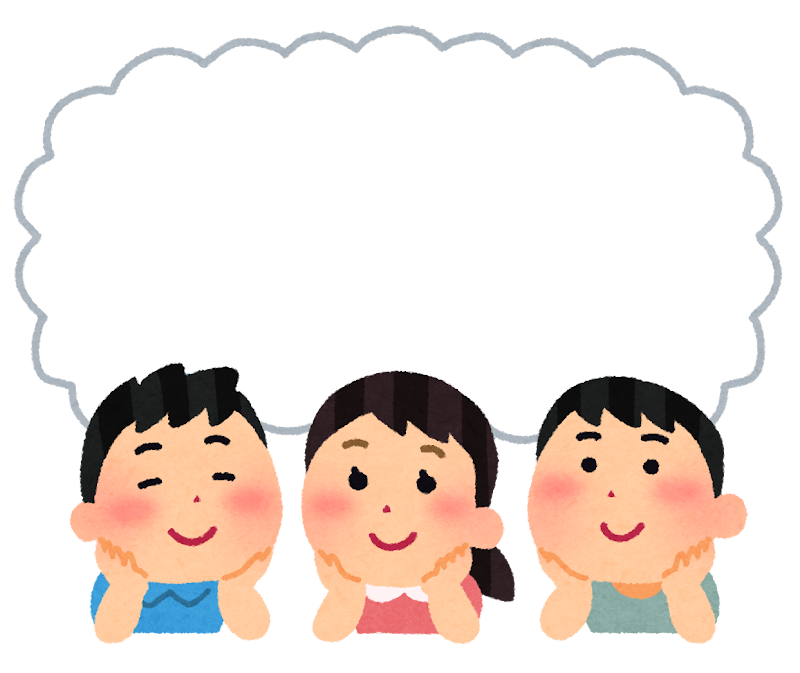
「アプリをダウンロードするとき、『アクセスを許可しますか?』と出たら、どうするのが安全かな?」
おうちのルールを決めてみよう!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。
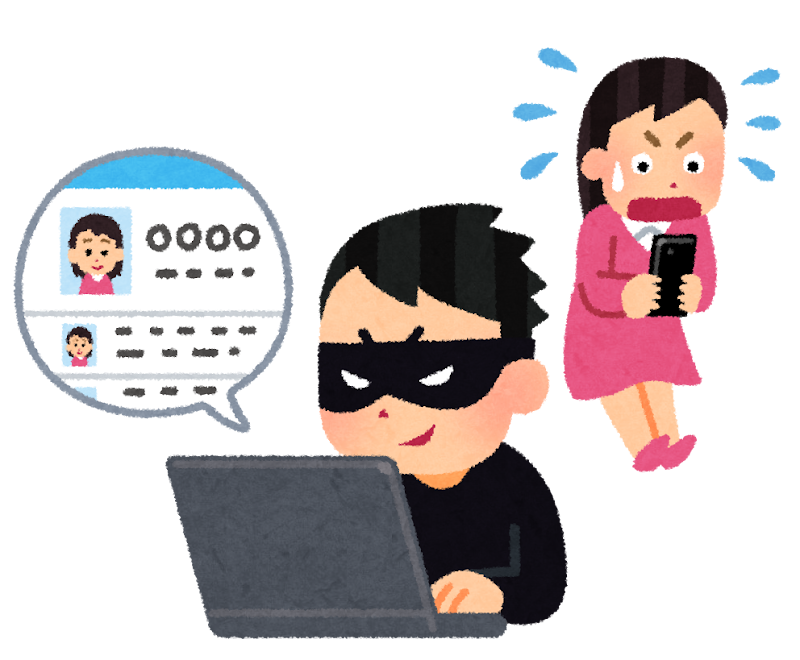
現代の社会では、インターネットを活用する機会が増え、家庭や学校、職場など、あらゆる場面でネットワークを利用することが当たり前になっています。しかし、その一方で、不正アクセスや情報漏洩(じょうほうろうえい)などの危険も身近なものとなっています。こうしたリスクを防ぐためには、ネットワークの仕組みやセキュリティについて正しく理解し、安全に活用する力を身につけることが大切です。
文部科学省の学習指導要領においても、情報通信技術を正しく活用する能力は重要視されています。特に高等学校の「情報Ⅰ」では、ネットワークの基本的な仕組みや、データを安全にやり取りするためのセキュリティ対策について学ぶことが求められています。また、小中学校の段階でも、インターネットを使う上でのルールや危険性について学ぶ機会が設けられています。
例えば、SNSで友達のようにふるまい、パスワードを聞き出そうとする「なりすまし」や、不正なメールを送り、相手にウイルスを開かせる「フィッシング詐欺」など、インターネット上にはさまざまな危険があります。こうした手口を知り、正しく対応する力を身につけることは、子どもだけでなく、大人にとっても必要なスキルです。
インターネットは便利である一方、正しい知識がないと危険に巻き込まれる可能性があります。だからこそ、ネットワークとセキュリティについて学ぶことは、安心してデジタル社会を生きていくために欠かせないものなのです。
おうちで
チャレンジ!
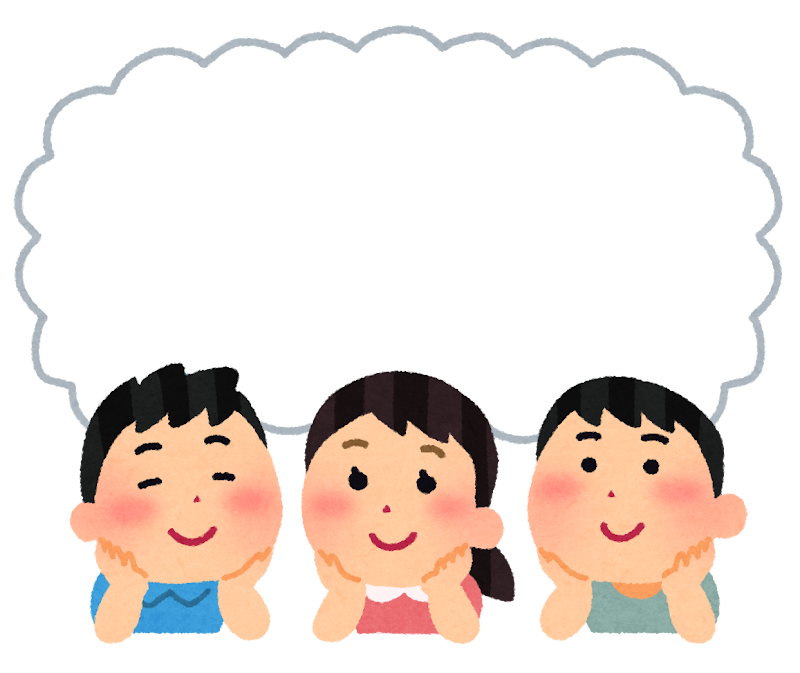
「電車の中でスマホを使っているとき、うしろの人にパスワードが見られていたら…?」
おうちで一緒に考えてみよう!

お気軽に
ご相談ください
※泉が丘校・東海校ではプログラミングも学ぶことができます。お気軽にご相談ください。





